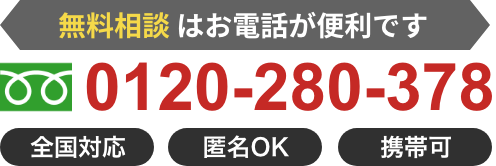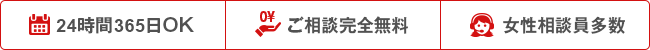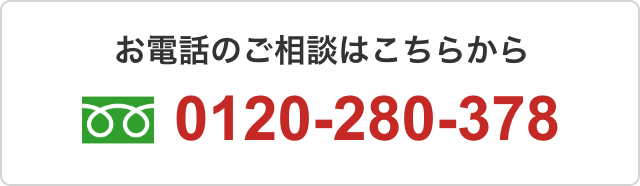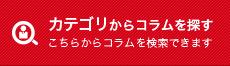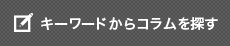最短で解決するために、離婚トラブルの解決が得意なお近くの弁護士にまずは無料相談してみませんか?

離婚の際の年金分割(ねんきんぶんかつ)とは、厚生年金や共済年金を決められた割合で分割する制度です。
年金分割という言葉を聞いたことがある人はいらっしゃるかもしれませんが、具体的にどのような制度で、いくら年金が増えるのかよく分からないのではないでしょうか?
今回の記事では、この年金分割制度について詳しく解説しますが、特に専業主婦にとってはありがたい制度ですから、もしも離婚を考えているのであれば、ぜひ参考にしてもらいたいと思います。
| 順位 |

|

|

|
|---|---|---|---|
| サイト名 |
 綜合探偵社MJリサーチ
|
 【配偶者の浮気調査専門】総合探偵社クロル
|
 総合探偵社AMUSE
|
| 総合評価 | |||
| 料金 |
初回限定のお得なパック料金あり
調査の掛け持ちゼロなので、本気度の高い方から好評 |
【電話相談が無料】
お金を払うかどうかはまずは見積りの後でOK 更に、他社よりも好条件での見積り提示が可能 |
全国一律3,980円~/1時間のため、
初めての方も依頼しやすい 調査結果が出なければ調査費用はなんとタダ |
| 特徴 |
メディア出演、警察捜査協力など確かな「実績」と20年以上の「経験」のあるベテラン・精鋭集団
|
配偶者の浮気調査に特化!
他の事務所では取扱い不可な高難易度調査も対応可能! 顧客満足度98%・調査件数32,000件と確かな実績がある総合探偵社 |
初回相談が無料、調査をリアルタイムで報告してもらえるので、安心のサービス
|
| 口コミ評価 |
価格設定と強力な証拠に定評あり
|
無料で見積り相談できるのが高評判
|
無料相談できるのが高評判
|
| メール相談 |
|
|
|
| 電話相談 |
|
|
|
| 料金の手頃さ |
|
|
|
| 公式リンク | 公式 | 公式 | 公式 |
年金分割とは|年金分割の基礎知識
早速、年金分割とはどのようなものなのかをまとめていきましょう。
年金分割制度の概要
年金分割とは、離婚時に被保険者である側(多くの場合は妻)が、もう一方の厚生年金や共済年金を分割できる制度になります。
《年金分割をした場合》
年金分割を受けた側▶65歳以降で受給できる年金額が増える
年金分割をされた側▶将来の年金額が減る
自営業などで夫婦ともに国民年金に加入している場合は対象にはならず、自分自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料納付期間により受給資格を満たしていないと、年金は受け取れません。
年金分割で得をするケース
この年金分割を活用するメリットがあるのは、あくまでも婚姻期間中に配偶者が厚生年金や共済年金を自分よりも多く支払っている場合になります。したがって、夫が自営業の場合に妻が年金分割を行おうと思っても報酬となる分がないので、年金分割が行なえないことになっています。
年金を受け取れるのは満65歳から
年金分割によって得られる年金は、年金を受給できる年齢である65歳になった時に通常の年金に上乗せされる形で支払われるため、年金分割をしたからと言ってその直後に受け取れるというわけではありません。
また、年金を全く支払っていなかったなど受給資格を満たしていない場合は、年金がもらえない=離婚時に分割した年金ももらえなくなります。
年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」がある
年金分割は、平成19年4月から実施された合意分割制度と、平成20年4月から実施された3号分割制度がありますが、この2つについて詳しく解説していきましょう。
合意分割制度
合意分割は、2007年4月1日以降に離婚した夫婦が、結婚していた期間の厚生年金の標準報酬部分を最大2分の1まで分割できる制度です。
分割の割合は夫婦の話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判で決めます。割合について合意ができたら、年金事務所に年金分割の申請をする必要があります。
夫婦共働きであった場合は、この合意分割制度に従って分割を行うことになります。分割の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について知るためには、日本年金機構から『年金分割のための情報提供請求書』を取り寄せてみましょう。
3号分割制度
3号分割の「3号」とは、国民年金の第3号被保険者である専業主婦のことを示しています。2008年4月から離婚するまで、第3号被保険者であった期間の夫の厚生年金の標準酬額の2分の1を、話し合いや調停などによらずに受け取ることができます。
ただし、自動的に分割されるわけではなく、離婚後2年以内に本人が年金事務所に分割の請求をする必要性があります。分割された年金は離婚後に妻が年金受給年齢に達すると、妻名義の老齢厚生年金として、終身支給されることになります。
年金分割制度が作られた背景
熟年離婚の特徴として、「価値観の違い」「第二の人生をスタートさせたい」という意見がとても多く挙げられます。しかし、このような理由では、離婚時に慰謝料を受け取ることができません。こうなると、特に収入のない専業主婦は「離婚後にどのように生活したらいいのか」が不安の種になります。
預貯金でまかなうことができれば良いのですが、中にはマイホームを売って現金化しなければならないといった人もいました。
従来も、熟年離婚をする場合には夫の退職金や年金についても財産分与の対象になるとする判例がありましたが、前述のような不安の解消を目的とし、平成19年4月から正式に、”夫婦が離婚した時には年金を分割するシステム”である離婚年金制度が法律によって認められ、スタートしました。
年金分割で年金がどれだけ上下するのか?
年金分割を行うことで、実際どのくらい年金が増えるのか、また、減るのかは誰しもが気になるところだと思います。しかし、これはケースバイケースになるので、いくら上下すると断定ができません。
ここでは、年金分割の計算例と自分で照会する方法について見ていきましょう。
50歳以上は年金見込額が照会できる
・50歳以上の人
・障害年金を受けている人
上記に該当する人ならば、年金分割による年金見込額を照会することが可能になります。「年金分割のための情報提供請求書」により情報提供の請求をした後に、「年金分割を行なった場合の年金見込額のお知らせ」が届けられるので、こちらを確認してみましょう。
▶年金分割のための情報提供請求書
情報提供請求に必要な書類
・年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本
自分で年金見込額を概算する方法
・50歳未満の人
・障害年金を受けていない人
上記に該当する方は、自分自身で試算しないといけません。大まかには、1年間の厚生年金の加入で額面月収(ボーナスは月割して加算)の約6.6%が1年間の年金額となります。ここではその計算例をご紹介します。
計算例①
|
【例】 |
計算例②
|
【例】 |
年金分割に関するよくある誤解
ここでは、年金分割に関して多くの人が抱いている誤解を解くために、詳細を解説していきましょう。
誤解①離婚すると夫の厚生年金の半分が受け取れる
夫の年金の2分の1がきちんともらえるわけではなく、対象となるのは夫が婚姻期間中に支払った分の厚生年金(共済年金)のみとなります。例えば、夫の厚生年金加入期間が30年間あったとしても、婚姻期間が10年間だった場合は、この10年間に支払った分しか年金分割の対象にはなりません。

誤解②自動的に2分の1が与えられる
実際に妻がいくらもらえるのかは、話し合いによって決まります。例えば、夫が「妻には自分の年金を1円たりとも渡したくない」と主張した場合は、どちらかが家庭裁判所に申立を行い、調停によって決めることになります。
誤解➂元配偶者が死亡した場合は年金をもらえなくなる
仮に、年金分割の結果、妻が分割された年金を65歳以降に受け取れるようになったとします。この際、妻が65歳になる前に夫が死亡したとしても、妻が生きている限りは分割された年金は支払われることになります。
年金分割の請求方法
具体的に、年金分割はどのようにして請求したら良いのでしょうか?合意分割、3号分割、それぞれの請求方法を解説していきましょう。
合意分割で請求する方法
①年金情報通知書の入手
まず、お伝えした「年金分割のための情報提供通知書」が年金分割には必要になります。
「年金分割のための情報提供通知請求書」に記入後、年金事務所に書類を提出すると、「年金情報提供通知書」が送られてくるので、こちらを見ながら年金をどのくらいの割合で分割するのかを、
・夫婦間の話し合い
・調停
・審判
・裁判
上記のいずれかによって決定します。
②分割割合の決定
夫婦間の話し合いにより決定する場合
夫婦当事者、またはその代理人が最寄りの年金事務所で年金分割の改定請求を行います。
《代理人を立てる際に必要な書類》
・委任状
《年金分割の改定請求に必要な書類》
・年金分割の合意書
・元夫婦双方の戸籍謄本
・双方の年金手帳
調停・審判・裁判で決定する場合
夫婦のどちらかが最寄りの年金事務所にて所定の手続をすることになります。
《請求手続に必要な書類》
・年金手帳
・夫婦双方の戸籍謄本
3号分割で請求する方法
年金事務所での手続
3号分割の場合は、年金分割を望む一方が年金事務所にて手続を行うことが可能で、分割割合は2分の1ずつと決定しているので、夫婦間の話し合いも不要となります。
特に複雑なことは何もなく、年金事務所では「年金分割の標準報酬改定請求」を行うだけで完了となります。
年金分割の注意点
本記事の最後に、年金分割の注意点についてもまとめていきましょう。
手続を行なわなければもらえない
くれぐれも、年金分割は自動で行なわれるものではないということを覚えておきましょう。夫婦のいずれか、または夫婦間の合意のもと、所定の手続を行なわないと得られるものは得られないということになります。
請求できる期間が決まっている
年金分割は原則として、離婚が成立してから2年以内に手続の制限が設けられています。もしも離婚してから既に2年以上が経過しており、それでも年金分割を行いたい場合は、離婚問題に注力している弁護士への依頼が有効です。
結婚前に納付したものは分割対象にならない
結婚前に〇年分の年金を納めていた場合であっても、それは夫婦間で分割できるものとして扱われません。お伝えしたように、分割できる年金は結婚後に納めたもののみが対象となります。
まとめ
離婚時の年金分割をテーマにした今回の記事はいかがだったでしょうか。年金分割の方法も、年金分割によって得られる額も、ケースバイケースになります。さらに詳しく知りたいという方は、年金事務所や弁護士への問い合わせが有効です。

綜合探偵社MJリサーチが運営する当サイトの相談窓口では、24時間浮気に関するご相談を受付中!
MJリサーチでは来店不要で相談・依頼まで行えるオンライン面談もご好評いただいております。遠方の方、多忙な方、感染リスクを考慮し外出を控えたい方も、お気軽にお問い合わせください。
※婚約・婚姻関係がない方からのお問合せはお受けできかねますのでご了承ください。
離婚に関する新着コラム
-
 浮気を理由に離婚すべきか?|絶対に後悔しないために知って...
浮気を理由に離婚すべきか?|絶対に後悔しないために知って...今回は浮気をされてしまったことで離婚すべきかどうかを判断する基準と併せて、離婚を回避する場合と離婚を希望する場合の対処法について解説していきたいと思います。
-
 不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前...
不貞行為と離婚・慰謝料の全知識|慰謝料の相場・離婚する前...不貞行為で離婚に至る場合、何をすべきなのでしょうか。この記事では、不貞行為で慰謝料請求をしたい、離婚の具体的な流れや知識を知りたいといった方へ向けて、不貞行為と...
-
 離婚時の慰謝料と養育費の相場|できるだけ高額にするための...
離婚時の慰謝料と養育費の相場|できるだけ高額にするための...離婚原因が相手にある場合、慰謝料を請求し離婚することができます。また、親権を持っていない親に養育費を請求することが可能です。ここでは、慰謝料と養育費をできるだけ...
-
 仮面夫婦と不倫の実態|離婚時に不倫を理由に慰謝料請求はで...
仮面夫婦と不倫の実態|離婚時に不倫を理由に慰謝料請求はで...二人の間に愛情が一切なく、関係が冷え切っており、会話もなくお互いに不倫をしていたりする夫婦は、実際の家庭にもあります。ここでは仮面夫婦の特徴や離婚しない理由、離...
離婚に関する人気のコラム
-
 数字で見る男女別不倫の割合|不倫をする心理と疑った時の対...
数字で見る男女別不倫の割合|不倫をする心理と疑った時の対...不倫の割合やきっかけ・不倫をする心理を知っておくことで、自分の夫や妻が不倫をしているかどうか見極める参考になります。ここでは、不倫の割合やきっかけ、不倫を疑った...
-
 離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと...
離婚前に別居する5つのメリット|別居を検討すべきケースと...いきなり離婚するよりも、別居を経てからのほうが納得のいく離婚ができるかもしれません。この記事では、別居をするメリットや、「離婚裁判」の際に別居をしておくことで有...
-
 【離婚したくない人必見】離婚危機の解決法とやってはいけな...
【離婚したくない人必見】離婚危機の解決法とやってはいけな...この記事では、「離婚したくない」のに、パートナーから離婚を切り出された方に向けて、離婚を回避する方法、離婚が認められてしまうケースなどを法律的な観点からも詳しく...
-
 離婚したい妻がとる行動と心理|離婚せずに夫婦関係を修復す...
離婚したい妻がとる行動と心理|離婚せずに夫婦関係を修復す...この記事では、離婚したがっている妻が取る行動・離婚したいと感じるようになった原因や心理・妻と離婚しないための方法などについて解説します。
離婚 コラム一覧へ戻る